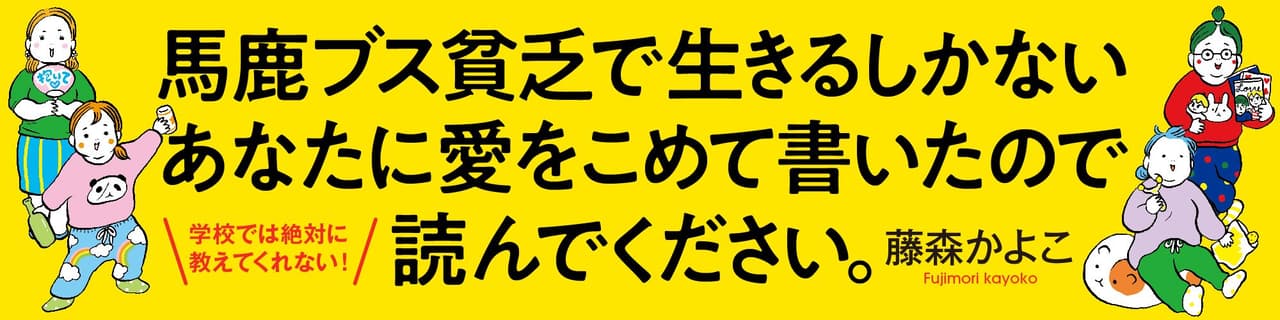米中欧の為政者は「コロナ禍」を政治的に利用したけれど、日本の為政者は何をしたのか?【藤森かよこ】
21世紀の日本の為政者は18世紀の清朝乾隆帝に及ばない
■乾隆帝は霊魂泥棒妖術騒ぎをいかに政治的に利用したか?
前述の中国学の泰斗フィリップ・A・キューンは、乾隆帝は単なる地方の迷信騒ぎを利用して、清王朝の潜在的に脆弱な政治的基盤を強くしたと推理している。
どのような理由が乾隆帝にそうさせたかについて、多くの点をキューンは指摘しているが、本文では主たる4点に絞って紹介する。
まず第一に、清王朝の出自たる満州族の弁髪を切って魂を盗む妖術は、清王朝の権威に対する潜在的反逆と乾隆帝は考えた。だから妖術使いの元締めを探索発見するよう官僚に号令をかけた。
清王朝立ち上げの頃に満州軍に投降した漢人は、満州族の髪型を受け入れなければならなかった。1645年には正式に薙髪令(ちはつれい)が布告され、髪型を弁髪にしないのは天命に背くとされた。しかし、この薙髪令への抵抗運動は地方では活発に繰り広げられた。
北方少数民族の満州人が立ち上げた清王朝は、多数派の漢民族による反乱が起きる可能性に常に脅かされていた。だからこそ、乾隆帝は、霊魂を盗む妖術の元締めを見つけ出し罰し、それを国民に見せつけねばならなかった(『中国近世の霊魂泥棒』71-73)。
第二に、霊魂泥棒妖術騒ぎが起きた揚子江下流地域である江南への監視を厳しくするのは、清王朝の基盤を強くすることに利益があった。
江南は、農業が豊かで商業が繁栄し、文化的にも学問的にも洗練された地域であった。「北京の食糧の多くは、江南から大運河を通って賄われた」(89)ので、中国の支配者は数世紀にわたり江南の指導層と争ってきた。特に江南の知識人を政治的にどう懐柔するかというのが北京の懸案事項のひとつだった(今の上海と北京の対立と似ている)。
満州人皇帝にとって、江南は退廃的で腐っている漢人文化のシンボルだった。満州人の美徳を侵食する悪徳は南から来る。だからこそ、江南で起きた迷信騒ぎについて皇帝は軽く見ることをしなかった(89-91)。
第三に民衆から生まれた妖術騒ぎそのものが、清王朝の統治の正当性と正統性を揺るがすので、事件の鎮圧に乾隆帝は乗り出した(111―113)。
なぜ民衆の間に霊魂泥棒妖術パニックが生まれるのか?それは、民衆が不安を抱えて生きているからだ。その不安が妖術の噂に触れ、不安が恐怖となり、集団的ヒステリーを生む。
では、なぜ民衆は集団ヒステリーを起こすほどに不安を抱えて生きているのか?それは、王朝の統治が民衆に満足と平穏を与えていないからだ。
「天命思想」とは言うまでもなく、「天は人間界から誰かを自分の子(天子)として選び、人間世界の支配権を委譲する。これが天命である。そうすることによって天は人間世界を支配する。天命を下された人間が皇帝となり、その支配権は子孫にも受け継がれていく」という考え方である。
民衆の間から妖術騒ぎが起きたことは、清王朝に天が下したはずの天命が機能していないことを示していた。つまり清王朝の衰退と滅亡を予言しているのかもしれなかった。だからこそ、乾隆帝は妖術騒動を一掃するために妖術使いを逮捕する必要があった。
第四に、乾隆帝には、皇帝の独裁権を守るために官僚たちを十全に機能させるとともに十全に抑圧するという矛盾した姿勢を強固に保持する必要があった。霊魂泥棒妖術騒ぎは、それを実践するいい契機を乾隆帝に与えた(227―67)。
そもそも、独裁制と官僚制は両立できない。官僚は決まったルールと手続きに則って物事を決定し実践する。独裁者は恣意的に決定し実行する。官僚制は独裁者の恣意性を抑制するように機能する。優秀な官僚なくしては統治できない皇帝ではあるが、官僚集団には皇帝自身の存在理由を無効にする潜在力があった。それを阻止するために、皇帝は有力な官僚に皇帝への直接的報告書を書き送ることを命じ、その報告書に自分の意見を自ら朱書きにして返送した。官僚に丸投げ一任することはしなかった。
乾隆帝は、江南地域を担当する官僚が、霊魂泥棒妖術騒ぎについて自分に早く報告しなかったことについて危惧を感じた。これは、官僚が官僚体制だけで事件を治めるつもりだったということであり、皇帝を蔑ろにしていることになると乾隆帝は考えた。
だからこそ、乾隆帝は、わざわざ地方の役人たちに厳しい調査を命じ、単なる地方の迷信騒ぎに官僚たちを総動員させた。この事件の責任を問われ、罰せられたり降格したり失脚した官僚は少なくなかった。この事件は、乾隆帝から見たら自分への忠誠が足りないと思えた高級官僚たちの粛清でもあった。
このようにして、乾隆帝は単なる一地域の噂話から起きた騒ぎでしかないことを、わざわざ国家的大事件にすることにより、清王朝への政治的文化的脅威を軽減した。と同時に、皇帝による官僚支配を徹底させた。